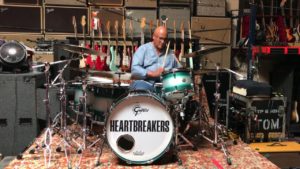スティーヴ・フェローンが在籍したアヴェレージ・ホワイト・バンドを聴いていると、
どうしてもあるバンドを思い出し、また比較してしまいます。鉄壁のリズムセクション、
ソリッドなブラス隊、そしてソウルフルなヴォーカル、これでもか!というファンクグルーヴを
繰り出すそのバンドの名はタワー・オブ・パワー。カリフォルニア州オークランドで結成された
彼らの音楽は、それを指してオークランドスタイルファンクと呼ばれる一ジャンルとして語られる程、
ポップミュージック界において、特に同業者達へ影響を与えました。
#85のヒューイ・ルイス&ザ・ニュース回において彼らに触れ、いつか必ず取り上げますと
述べましたが、思ったよりも早く書くことが出来ました。
バンドの出発点は68年に創設メンバーであるエミリオ・カスティロとステファン・カップカが
出会った所から始まります。ただしこのバンドはメンバーが多く、またその変遷も激しい為、
それらについては割愛します。興味がある人はウィキ等で。
当初彼らは『ザ・モータウンズ』と名乗っていた、もしくは周りに勝手に名付けられたらしいです。
カスティロは後のフィルモア・ウェストの前身、フィルモア・オーディトリアムへの出演をオーナーである
ビル・グレアムへ交渉しようとしますが、『ザ・モータウンズ』では彼が出演を認めてくれないと
考え、バンド名の変更を容認するようになります。そうして70年までにはタワー・オブ・パワーという
新しいバンド名が確定し、当時ビル・グレアムが設立して間もないサンフランシスコレーベルから
1stアルバム「East Bay Grease」をリリースします。
72年にはワーナーへ移籍し、二作目となる「Bump City」を発表。アルバムはR&Bチャートで16位、
シングルもTOP40に入り、徐々に世間への認知度を高めていきます。
73年、3rdアルバム「Tower of Power」をリリース。上はオープニングナンバー「What Is Hip?」。
百聞は一聴に如かず、問答無用のこの曲を聴けば彼らの凄さがわかるはず。
1stシングルである「So Very Hard to Go」は彼らにとって最大のシングルヒットとなりました
(ポップス17位・R&Bチャート11位)。本作はセールス的にバンドにとって最大の成功作と
なりました。ポップスチャートで最高位15位を記録し、ゴールドディスクに認定されます。
74年発表の「Back to Oakland」。セールス的にこそ前作には及びませんでしたが、彼らの
最高傑作と評するリスナーが絶えない名盤です。オープニングとエンディングを飾るナンバー
「Oakland Stroke」。最初は0:53、最後は1:08と短い曲。短くて良いでしょう、
あまりにも凄すぎて、この尺でも十分です。上はUP主が2曲を繋げたらしいですが、
オープニングもフェイドアウトで終わっているのに、境目が全く分かりません。一体どうやって
作ったのでしょうか?・・・・・ナゾの技術・・・才能のムダ・・・・・
(._+ )☆\(―.―メ)そこまでは言われる筋合いはない!
(※と、思っていたのですが、更に調べたところ、昔シングル盤で発売されたことがあったらしいです)
https://youtu.be/CfYy914PXwc
私が思う本作のベストトラックは二曲あるのですが、上はその甲乙付けられない内の一つである
「Can’t You See (You Doin’ Me Wrong)」。あまりごちゃごちゃは言いません、聴いて下さい。
https://youtu.be/RlLVRGb7g7Q
インストゥルメンタルパートが取りざたされる事の多い彼らですが、ヴォーカル曲も秀逸です。
ヴォーカリストは割と入れ替わりが激しいバンドでしたが、黄金期に在籍したのがレニー・ウィリアムズ。
レニーの素晴らしい名唱が堪能出来るのが上の「Just When We Start Makin’ It」。
私にとってもう一つのベストトラックがこれ、「Squib Cakes」。これもあまりごちゃごちゃは
言わないつもりでしたが … 少しだけ言わせて下さい・・・・・・・・・ごちゃごちゃ ……………
(._+ )☆\(―.―メ)言うとおもった!!!
完璧なグルーヴ、ソロプレイヤー各々のアドリブ、ブラスのソリ、どれを取っても超一級品の演奏。
全編に渡って素晴らしいプレイのオンパレードですが、やはり聴き所は4:55からのオルガンと
ギター・ベース・ドラムのリズム隊によるプレイ。途中からはワンコードになり、主役は完全に
ベースとドラム。派手な耳を引くソロプレイではない、リズムの掛け合いであるのに、これ程までに
甘美と言っても過言ではないグルーヴを私は他に知りません。6:02でコードチェンジする部分は、
カタストロフとでも呼ぶべきそれまでのテンション感が一気に弾ける鳥肌モノのパートです。
その後、セールス的にヒットを上げる事はなく低迷していたバンドでしたが、ヒューイ・ルイスの
力添えなどもあり地道に活動を続け、今日まで解散することなく、根強いファン、また同業者達からの
応援を受け続けています。
レコードセールス面だけを見れば、ゴールドディスクが一枚、TOP20入りしたシングルも一枚と、
決して大成功を収めたバンドではありません。インストゥルメンタルの比重が多いので、一般ウケしづらい
のは如何ともし難い所でしょう。卓越したシンガー達が在籍したバンドですので、もっとバラードなどを
フィーチャーした売り方をすれば、ひょっとすると違った結果があったかも(たらればですけど…)。
しかし彼らは、自分たちの本分はグルーヴを重視したファンクミュージックであるとの自負が
あったのでしょう。そして、その様な姿勢を貫く彼らだからこそ、コアなリスナーや同業者達から常に
尊敬の念を受け続ける事が出来たのではないでしょうか。
一人か二人しかいない読者の中には、ドラマーについて全然書いてないじゃん、と思われた方も
いるかもしれません。…………… いない … かな?・・・・・゜:(つд⊂):゜。。
そうです。タワー・オブ・パワーのドラマー デヴィッド・ガリバルディについては、次からの
テーマとするためにあえて触れませんでした。という訳で次回からはデヴィッド・ガリバルディを
取り上げていきます。